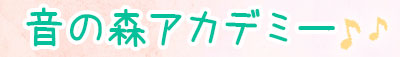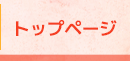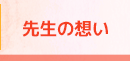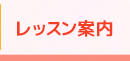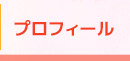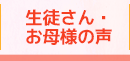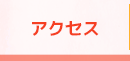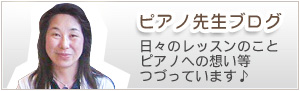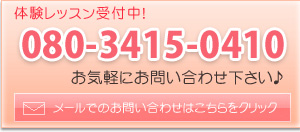ピアノ先生ブログ
ちょっとコーヒーブレイク 千葉市緑区ピアノ教室のぶこせんせのコラム
本日も晴天なり☀︎
早朝、生垣の柊に消毒をしてにわかてんとう虫駆除対策
どうか剪定した柊が害虫にやられませんように!
さぁ、待ちに待った学生時代の友人と上野駅で待ち合わせの日
私が以前から行ってみたかった湯島の旧岩崎邸を散策しました
地下鉄千代田線湯島駅から徒歩三分ほど
目の前には、鹿鳴館の建築家が建てた絢爛豪華な洋風建築のお屋敷が。
三菱財閥の底力を結集した広々とした敷地
ゆっくりと一部屋一部屋を順路のとおりに廻って、室内装飾の技術に驚きました。
明治時代にこれだけの技術があって日本という国はホントに素晴らしい❗️
明治時代にすでにおトイレは洋式の水洗トイレなのですよ❗️
これまた驚き
室内に置かれたピアノはまさに最近出されているような、コンパクトなグランドピアノ
時代の最先端を走っていたのです
明治時代に。
ご婦人のお部屋の壁紙はサーモンピンクで、天井は刺繍されたお花の模様で作られています。
なんて手の込んだお屋敷でしょうか。
タイルはイギリスの有名な陶器メーカー・ロイヤルドルトン社製
家具のキャビネットはイギリスの物で重要文化財
このお屋敷で様々な国の方と商談をしたり音楽演奏を楽しんだりしたのでしょう。
古の昔に思いを馳せる時間でした。
ピアノ練習方法4 千葉市緑区ピアノ教室のぶこせんせのコラム
早朝は爽やかで気持ち良いです!
この時期は早起きをおすすめします
8時を過ぎたらじわりじわり暑さが増してきますね☀︎
今日の真夏日に8時過ぎから大椎中学校で草取りが行われました。
子供が三年間の間に保護者が役員にならなかった場合は協力員として草取りに参加する義務があります。
集まった保護者で学年ごとに分けられたエリアの草取りを行いました。
約1時間、汗だくになって雑草取りをしました。
ジャングル地帯の校庭がスッキリ❗️
同級生のお母さん方と雑談後、解散
帰宅後すぐにシャワーして全身スッキリ
午後からは、まなちゃんのレッスン
4月から始めたレッスンは二ヶ月になります。
五本の指で音の階段を登って降りての繰り返し
右利きのまなちゃんは左手の練習を多くして、左手の動きを機敏に❗️
できれば、左手の階段を何度も往復して練習することが上手になるコツ
と、いうことで。
テクニック練習がいかに大事かをお伝えしたいと思います!
バーナム、ハノン、ツェルニー、トンプソン等のエチュード練習曲を毎日弾くことは上達の近道になります。
たとえば、野球選手のことを考えてみましょう。
アメリカのメジャーリーグで1998年に大活躍したマクガイヤ選手やソーサ選手は、たくさんホームランを打てたからと言ってバットを振る練習をしないと言うことはありません。
試合がある日も無い日も、試合で打てても打てなくても、毎日練習をします。
バットを振る練習だけではありません。体を柔らかくするための柔軟体操や、足腰を鍛えるためのランニングや筋力トレーニングも決してさぼったりしません。
それでは、プロのピアニストはどうでしょうか。
やっぱり毎日何時間もの練習を欠かすことはありません。
一流のプロが毎日一生懸命練習しているのであれば、一流ではない人が練習をさぼっていて上手になるはずがありません。
上手になるためには、毎日練習することがとても大切です。そして、一番大切なのはエチュードの練習です。
エチュードを練習する意義
エチュードを練習することにはどのような意義があるでしょうか。それは、スポーツ選手が行う「柔軟体操」や「筋力トレーニング」、また試合の感覚を養う「実践的トレーニング」と同じような意味があります。
エチュードの目的は大きく分けて次のようになります。
力強いタッチを身につける。※タッチとは鍵盤を弾く力のことです。
指をできるだけ大きく広がるようにする。
素早く正確に指を動かせるようにする。
レガートやスタッカートなどの奏法の練習。
そして、その他に強弱の使い方や、フレーズの歌い方などの練習などが盛り込まれている場合もあります。
エチュードの目的は「指を自分の思うがままに動かせるように訓練する」こと
自分の思うように指が動かせるようになれば、どんな曲もすぐに弾けるようになるものです。
エチュードはそのために、自分に力をつける練習なのです。
効果的な練習方法
エチュードの効果的な練習の仕方には次の二つのポイントがあります。
1.毎日決められた回数を必ず弾く。
たとえ弾けるようになったとしても、次のレッスンまで毎日弾くべきです。最低でも5~6回は弾くようにしましょう。また、どんなに忙しくても1回は必ず弾くという決意が大切です。
2.定期的に前へ戻って復習する。
一度できるようになったからそれでいいというわけではありません。
練習で大切なのは何度も繰り返して行うこと
一ヶ月に一度はそれまで練習したエチュードをおさらいするのは効果的です。
できれば何曲かごとにまとめて弾くことをおすすめします。その時にもし、自分が弾けなくなってしまった部分があるなら、その部分を重点的に練習しましょう。
創意工夫が大切
人はそれぞれ違います。ある人がうまくいったからと言って、同じ方法で別の人がうまくいくとは限りません。自分にとって、もっともふさわしい練習方法は自分で探さなければなりません。ここで述べられたことや、レッスンで先生に教えてもらったことを自分にどのように当てはめていくか、よく考えましょう。
そして、うまくいかないところをどうやって弾けるようにするか、自分自身で工夫して練習して下さい。
自分で工夫して練習をする人は必ず上手にできるようになります。
肝心なのは「あきらめない」ことと「なまけない」ことです。
みなさん、ぜひがんばって下さい。
❤︎音の森アカデミー❤︎
体験レッスンを受け付けています
お申し込みはお電話☎︎080-3415-0410
またはホームページからお願いいたします
ピアノ練習方法ポイント3 千葉市緑区ピアノ教室のぶこせんせのコラム
真夏日の5月30日
汗だくの幼稚園生のレッスン日
あまりの暑さにおでこに汗してお出ましです
習いはじめの生徒さんはきちんと指番号を守って練習してきます
ところが、だいぶスラスラ弾けるようになり、初見も弾けるようになってきた頃に指番号があまくなりがちな生徒さんがちらほら
なんだか弾きにくそうな指使いだしフレーズが途切れて聴こえます
やはり、指使い・指番号はだ・い・じ
なぜかと言いますと…。
指にはそれぞれ右手も左手も親指から小指に向かって1,2,3,4,5と番号がつけられています。
これが指番号です。
楽譜を注意深く読むと、音符の上か下に数字が書いてあることがあります。
その数字は、その音を何番の指で弾くべきかを表したものです。これが運指つまり指使いです。
では何のために指使いが決められているのでしょうか。
その理由として主に三つのことが考えられます。
フレーズや音階を切れ目無く弾くために、もっとも効率の良い弾き方を示す。
特定のリズムをはっきりさせるために、ふさわしい弾き方を示す。
特定の指のさばき方の習得、又は特定の指を訓練するための練習。
このように、指番号はただ適当につけられるわけではありません。
もちろん、指番号を無視して、自分勝手な指使いでもピアノを弾くことはできます。
でも、そういう人の演奏は、メロディの流れがぶちぶちと切れていたり、変なところで演奏が止まったりして、聴いている人にとってはとても気持ちの良い演奏とは言えません。
また、自分勝手な指使いで練習していると、ピアノを上手に演奏するための大切な指さばきの技術が身につきません。
ですからそう言う人は2~3回練習してすぐ弾けるような曲はだいじょうぶですが、ちょっと難しい曲になると途端にたちうちできなくなり、同じ曲を何ヶ月練習しても上手に弾けるようにならないと言うお手上げ状態になってしまいます。
楽譜に書かれている指番号はピアノのテクニックを習得するための最も重要なことがらです。
たくさんの指使いを習得することによって、どんな曲でもぱっと弾けるようになるための指のさばき方を覚えるのです。
先生に注意された時だけではなく、普段の練習から自分で指番号を読んで、それを忠実に守るように心がけましょう。
と、いうわけでとってもとっても重要なことなのですよ❗️❗️
どうぞ面倒臭がらず、片手練習のときからしっかり指使いを守って練習に取り組んでくださいね!
音の森アカデミー
体験レッスンを受け付けています
お申し込みはお電話☎︎080-3415-0410 またはホームページからお願いします
ピアノ練習方法2 千葉市緑区ピアノ教室のぶこせんせのコラム
急に夏日を思わせる蒸し暑さです
こんなときは体調が不安定になりやすいので無理せず過ごしましょうね
午後3時からのレッスンはさすがに室内は蒸し暑く冷房を入れてのレッスンです
小学三年生のさくらちゃんはそろそろメトロノームが必要な時期です!
今日のレッスンでは速度のお勉強
♩=96 どれくらいの速さでしょうか
ゆっくり歩くぐらい
メトロノームに合わせて弾いてみました
なるほど❗️
さくらちゃんは数回弾いてこのテンポで曲をしあげました
さくらちゃんのお母さまとメトロノームを準備する打ち合わせをしました。
本日はメトロノームのお話し
メトロノームは決められた速さで「カチッ、カチッ」とリズムをきざむ機械です。
こんな機械はあってもなくてもどうでも良いように思えるかもしれませんが、このメトロノームは音楽の練習には欠かせない、とても重要な機械なのです。
どのように使うか
音楽を演奏するときに、どのくらいの速さで弾くかを考えるのは大切なことです。
それぞれの曲には、その曲にふさわしい「速さ」があります。
ピアノを習い始めて少したつと、楽譜の上の方にイタリア語で“Moderato”(モデラート=中ぐらいの速さで)とか“Allegro”(アレグロ=速く)という言葉が書かれるようになります。
これは、その曲の速さを表している言葉
でも、一口に中ぐらいの速さとか、速く弾くとか言われても、人によってその速さの感じ方は変わります。
メトロノームはその速さの基準を示してくれる機械
メトロノームの速さを決める目盛りにはモデラートやアレグロなどの楽語が書かれています。
その曲に書かれている速さとメトロノームの目盛りを合わせます。それからメトロノームを動かして、その音に合わせてピアノを弾きます。
まずはゆっくりしたテンポに合わせて練習
そして、弾けるようになったら目盛りを一つずつあげて、それを続けて最後に目標の速さに着くまで練習を積み重ねていきます。
なぜメトロノームを使うのか
人間は機械ではありません。
ですから、ピアノを弾いていても自分では気づかないうちに速くなったり遅くなったりしています。
でも、それでは聞いている人が落ち着かないのです。
強く弾いたり弱く弾いたりするのを自分でコントロールするのと同じように、速く弾いたり遅く弾いたりすることもコントロールできなくてはなりません。
そのためにメトロノームを使って一定の速さで弾く練習をするのです。
これは音楽を練習する人全員が必要な練習
速さを意識せずに練習している人にはテンポ感が育ちません。
テンポ感とは「曲の速さを感じ取り、それをコントロールする感覚」のこと。
テンポ感のない人はつねに行き当たりばったりの演奏になりがち
曲を速くも遅くも演奏できないのです
例えるなら、アクセルの踏み方もブレーキのかけ方も知らない人が車を運転するようなもの
テンポ感を育てるために、メトロノームを使った練習はとても効果的
いつ頃から使うべきか
自分で音符が読めるようになり、音符の長さを理解して拍を数えて弾けるようになったなら、もうメトロノームを使えます。
少なくとも、楽譜に速度を表すAllegro”“Moderato”などの楽語や、メトロノームの速度を表す数字が出てくるようになったら必要です。
また、キーボードや電子ピアノにはリズムを鳴らせる機能が付いている場合もあるので、それで代用することも可能です。
ただし、お子さんが小さいうちは、メトロノームの目盛りを設定してあげるのはお母さん方の役割となるでしょう。
メトロノームはとても役立つ、便利な機械です。どうかそれを有効に使って自分の(お子さんの)練習に役立てて下さい。
音の森アカデミー
体験レッスンを受け付けています
お申し込みはお電話080ー3415ー0410・ホームページからお願いします
ピアノ練習方法ポイント1 千葉市緑区ピアノ教室のぶこせんせのコラム
少し蒸し暑さが増してきました
少しでも爽やかな気分で過ごしたいです!
ピアノの生徒さんは女の子・男の子、それぞれレッスン中の言葉に違いがあります。
比較的女の子はポジティブ志向
男の子はというと…、ナイーブな面がちらほら
今日はアンポジティブ的にならないための練習の仕方をお伝えしましょう
ピアノの特徴として、教わったから上手になると言うものではありません。
理由は、教わったことを身につけなければならないから
そのためにはどうしても練習が必要です!
ですが、練習は一見単調な訓練も含まれるため、決して面白いと言うほどのことではありません。
そして、辛抱強さや根気が求められます。
小さな子供に対して、そのように面倒くさいことを自主的に行うよう期待するのは難しいでしょう。そこで、お母さん・お父さんの出番です。
例えば、プロ野球の球団には必ず監督とコーチがいます。コーチは監督の指示に従い選手達を練習させ、どの選手がどういう状態にあるかを監督に報告したり、個々の選手にアドバイスをしたりします。
ピアノの先生は週に一回生徒に会って、どういう練習をすれば良いかアドバイスを与えます。すなわち監督と同じ役割です
ここで重要なのはそのアドバイスをどの程度生徒が把握できるかと言うこと
どれだけわかりやすく教えたとしても、小さな子供の記憶力や理解力には限界があります。
最も大切なことは次のレッスンまでどういう練習をするかということ
そこで、コーチとして練習を見守るお母さん・お父さんが必要なのです。
ではどのように子供達の練習をコーチできるでしょうか。
一つは根気よく励ましながら一緒に練習する方法。
二つ目はスパルタ式で強制的に厳しく練習させる方法。
私としては一つ目の方法をおすすめします
「家族で一緒に楽しむ」というスタンスでピアノを習う方がずっと楽しいと思います。
☝️コーチの役目として
客観的なアドバイスを与えるのもコーチの大切な役割
例えば、指の形や姿勢が崩れていたり、音を間違えていることに気づいていなかったり、指使いを間違えていたり、やみくもに速いテンポで弾いていたり。
そういうときにコーチから注意を受けるなら、レッスンに行く前にその部分を修正することができるかもしれません。
小さいうちは自分では気づかないことがたくさんあります。ですから、基礎的な部分の誤りを誰かにアドバイスしてもらうことが必要です
生まれながらにピアノを弾ける人は一人もいません。できなくて当たり前なのです。
曲がりなりにもピアノを弾けるようになったとすれば、それは努力が実っている証拠なのです。
ですから、うまくいったら大いにほめ、うまくいかないときは大いに励ましてください。
そして、お子さんが自発的に練習できるようになるまで決して焦らずに長い目で練習をサポートしてあげてください。
お子さんが「わからない」と言う時
練習の時に、お子さんが「わからない」と言うことがあるでしょうか。このお子さんが言う「わからない」には次のような意味があると考えられます。
1.自分で考えるのが面倒なので変わりに答えを出して欲しい。
2.別のことをしたいのでやる気がない。
3.とにかく、自分をかまって欲しい。
4.よく考えたけど本当にわからない。
お子さんの性格やその場の状況によってどういう意味の「わからない」なのかを判断しなければなりませんが、決してそれを無視しないで下さい。
また、直接的な答えをいきなり与えるのも好ましくないので、できればヒントをたくさん与えて自分で気づくようにし向けることです。
そうするなら、記憶が確かなものになりお子さんの発達段階における「教師期待効果」を生み出すことになります。
「教師期待効果」というのは、心理学的な現象ですが、親や教師が子供の正しい答えを期待して辛抱強く待つなら子供の成績が上昇するというものです。
期待感が無ければ、それは「無視」や「答えを待たない」と言う態度に現れ、子供はそれを敏感に感じ取るそうです。
お子さんの未来を大いに期待し、辛抱強く答えを導いて下さい。
「この子はきっとできる」と思うことが大切ですね!
でも、ご両親もわからないときは、「レッスンの時に先生に聴きましょう。」と言って下さい。
そして、次のレッスンに繋いでいただきたいと思います
✨音の森アカデミー✨
体験レッスンを受け付けています
お申し込みはお電話☎︎ ・ホームページからお願いします